コラム

外壁に発生した黒い汚れを見て、カビかもしれないと不安を感じている方も多いのではないでしょうか?外壁のカビは見た目の問題だけでなく、建物の寿命や住む人の健康にも影響を与える深刻な問題です。
本記事では、外壁にカビが発生する5つのおもな原因と、放置した場合に起こる4つのリスクを解説します。ぜひ本記事を参考に、外壁カビの早期発見と適切な対策を実施してください。
外壁にカビが発生する原因は、環境条件や建物の状態など複数の要因が重なることで起こります。
ここでは、以下5つの原因を解説します。
それぞれ見ていきましょう。
カビの発生にもっとも大きく関わっているのが水分です。
カビは菌類の一種であり、その活動や繁殖には水分が欠かせません。
そのため、外壁が長時間湿った状態に置かれると、カビの発生リスクは著しく高まります。
たとえば、雨だれが伝いやすい窓サッシの下や、エアコンの室外機周辺はとくに注意が必要です。
また、室内と屋外の温度差によって生じる結露も、カビの温床となります。
冬場に暖房で暖められた室内の湿気が、冷たい外壁の内部で結露し、壁の内側からカビを繁殖させるケースも少なくありません。
こうした水分をいかに早く乾燥させるかが、カビ対策のポイントです。
外壁に付着したホコリやチリなどの汚れは、カビにとって格好の栄養源です。
カビは汚れに含まれるわずかな有機物を分解して、エネルギーを得て繁殖するためです。
一見きれいに見える外壁でも、目に見えない排気ガスの油分や黄砂、植物の花粉や樹液、鳥のフン、虫の死骸などが付着しています。
交通量の多い道路沿いの家は油分を含んだ汚れが付きやすく、公園や森林の近くでは植物由来の汚れが飛来しやすい傾向にあります。
こうした栄養源が豊富にあると、水分さえあればカビはあっという間に広がってしまうでしょう。
定期的な洗浄でこれらの汚れを取り除くことが、カビの発生を抑制するうえで効果的です。
日当たりの悪さは、カビの繁殖を助長する大きな要因です。
カビは紫外線に弱く、湿った状態を好む性質があり、太陽の光が当たりにくい場所はカビにとって絶好の住処となるからです。
とくに、家の北側の壁面は一日を通して日陰になることが多く、カビの発生がもっとも多い場所として知られています。
隣家との距離が近かったり、高い塀や樹木があったりして日差しや風が遮られる環境も注意が必要です。
日当たりや風通しが悪いと、雨や夜露で濡れた外壁が乾きにくくなります。
その結果、壁面が長時間湿ったままになり、カビの繁殖に適した環境が維持されてしまいます。
外壁材自体の状態も、カビの発生しやすさに大きく影響します。
新築時の外壁には塗装による防水機能がありますが、紫外線や雨風にさらされることで経年劣化は避けられません。
塗装が劣化して防水性が低下すると、外壁材が雨水を弾かずに吸収しやすくなります。
壁が常に水分を保持する状態となり、カビの温床になってしまうからです。
リシンやスタッコ仕上げのような、表面がザラザラした凹凸の多いデザインの外壁材も注意が必要です。
この凹凸部分にホコリなどの汚れや水分がたまりやすく、カビの発生を促してしまいます。
定期的な塗装メンテナンスで防水機能を回復させることが、カビから家を守るうえで肝要です。
家の周辺環境、いわゆる立地条件もカビの発生リスクを左右します。
住んでいる場所によっては、カビが好む環境が自然に形成されてしまうためです。
たとえば、川や湖・田んぼなどが近くにあるエリアは、年間を通して湿度が高くなる傾向があります。
空気中の水分量が多いため、外壁が乾燥しにくく、カビが発生しやすくなるからです。
また、公園や森林、畑など植物が多い場所も注意が必要です。
植物は水分を保持し、土壌には多くの菌類が存在するため、カビの胞子が風に乗って飛散しやすくなります。
風通しの悪い建物の密集地や、湿気がたまりやすい谷地なども同様にリスクが高いといえるでしょう。
外壁に付着する黒や緑の汚れは、一見するとすべて同じに見えるかもしれません。
しかし、これらはカビやコケ、藻のいずれかである可能性があり、それぞれ以下のように性質が異なります。
| カビ |
|
| コケ |
|
| 藻 |
|
これらは混在して発生することも多く、正しい対処のためには違いを理解しておくことが大切です。
外壁にカビを見つけても「まだ大丈夫だろう」と、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、カビを放置することは、見た目の問題以上に深刻な事態を引き起こす可能性があります。
ここでは、外壁のカビを放置した場合に起こりうる4つのリスクを紹介します。
詳しく見ていきましょう。
外壁のカビは、建物の寿命そのものを縮める要因となります。
カビは単に表面に付着しているだけでなく、菌糸と呼ばれる根を素材の内部にまで伸ばしていくためです。
この菌糸が塗装の膜を破壊し、本来の防水機能を低下させてしまいます。
防水性が失われた外壁は雨水を弾けなくなり、壁自体が水分を吸収して常に湿った状態に。
水分を含んだ外壁材は、ひび割れや剥離を起こしやすくなります。
さらに症状が進行すると、建物の構造体である柱や断熱材にまで湿気が達し、腐食を引き起こす危険性も出てきます。
外壁のカビは、家の見た目を著しく損ない、資産価値の低下に直結します。
おしゃれなデザインの家でも、外壁がカビで黒ずんでいると、それだけで古びて管理が行き届いていない印象を与えてしまうでしょう。
これは、将来的に家を売却する際に大きなデメリットとなります。
不動産の査定において、外壁の状態は重要なチェック項目の1つです。
カビが生えた物件は、買い手から敬遠されたり、大幅な値引き交渉の材料にされたりする可能性が高くなります。
カビの除去や外壁の補修にかかる費用を見越して、査定額そのものが低く評価されることも少なくありません。
外壁のカビは、そこに住む家族の健康を脅かす可能性があります。
カビは目に見えないほど微細な胞子を空気中に大量に放出し、私たちは知らず知らずのうちにそれを吸い込んで生活しているためです。
外壁に発生したカビの胞子は、風に乗って窓や換気口から室内に侵入します。
この胞子を吸い込むことが引き金となり、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、アトピー性皮膚炎といった症状を発症、または悪化させることも。
とくに、免疫力の低い小さな子どもやご高齢の方、もともとアレルギー体質の方がいるご家庭では、より深刻な影響が懸念されます。
家族の健康を守る観点からも、カビの放置は避けるべきです。
カビの放置は、最終的に修繕にかかる費用を増大させます。
何事も「早期発見、早期対処」がもっとも経済的であることは、家のメンテナンスにおいても同じです。
発生初期の軽度なカビであれば、比較的安価な洗浄作業で除去できるケースがほとんどです。
しかし、対応が遅れてカビが外壁の奥深くまで根を張り、塗膜の劣化や外壁材の損傷を引き起こしてしまうと、単なる洗浄では解決できません。
その場合、下地の補修や全面的な再塗装が必要となり、工事費用は数十万円から百万円以上に及ぶこともあります。
「安く済ませるつもりが、放置した結果、かえって高くついた」という事態を避けるためにも、早めの対応が賢明です。
外壁にカビを発見したとき適切な判断をするには、自分でできる作業の範囲と、潜むリスクを正しく知っておくことが大切です。
ここでは、自分でカビ取りを行う際の具体的な方法と注意点を整理して紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
軽度のカビであれば、適切な道具と方法により自分で除去できます。
まず中性洗剤を水で薄めた溶液を用意し、柔らかいブラシやスポンジで優しくこすり洗いをします。
カビ取り専用の洗剤を使用する場合は、外壁用と明記された製品を選びましょう。
カビキラーなどの塩素系漂白剤を使用する場合は、外壁を傷める可能性があるため、使用前に目立たない部分で試すなど注意が必要です。
洗浄後は必ず大量の水で洗い流し、十分に乾燥させることが大切です。
作業は晴れた日の午前中に行い、夕方までに乾燥させることで、カビの再発を防げるでしょう。
外壁のカビ取りを行う際は、自宅の外壁材の種類を確認することが不可欠です。
なぜなら、外壁材によっては、間違った掃除方法で傷を付けたり、変色させたりするおそれがあるためです。
たとえば、金属系や窯業系のサイディングは、硬いブラシで強くこすると表面のコーティングが剥がれてしまうことがあります。
また、モルタルやリシンのような塗装仕上げの壁は、使う洗浄剤との相性によっては色落ちする可能性も否定できません。
本格的に洗浄を始める前に、まず目立たない場所で洗浄剤を少量試しましょう。
外壁材の種類や状態が判断できない場合は、専門業者に相談するのがおすすめです。
▼カビ汚れの落とし方について詳しく知りたい方はこちら
【場所別】カビ汚れの落とし方と5つのカビ用薬剤の特徴を解説
2階以上の高所にカビが発生している場合は、安全面を考慮して専門業者へ依頼しましょう。
脚立やはしごを使った作業は、転落事故のリスクが高いためです。
とくに危険なのは、水を使った洗浄作業です。
足元が濡れて滑りやすくなり、バランスを崩す可能性が高まります。
専門業者は適切な足場を設置し、安全帯を装着して作業を行います。
高所作業の経験と技術により、効率的かつ確実にカビを除去できるため、費用対効果を考えても業者依頼が賢明な選択といえるでしょう。
外壁のカビは、湿気や汚れ、日当たりの悪さなど複数の原因が重なって発生します。
放置すると建物の劣化や健康被害、資産価値の低下など深刻な問題につながるため、早期の対処が肝心です。
ビカンテックの「ビカン工法」なら、特殊洗剤でカビを根元から除去し、防カビ・防菌処理により長期間美観を保てます。
素材を傷めることなく、リフォームよりも低コストで施工可能です。
まずは汚れの状況について、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
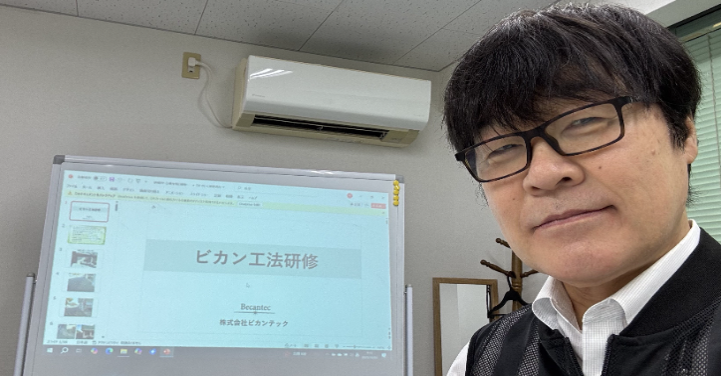
平田愼二Hirata Shinji
株式会社ビカンテック
営業部
プロフィール
2010年よりビカンテック加盟店募集営業・加盟店の開業支援、数多くの加盟店との連携を取りながら営業・施工応援に従事。
日々加盟店の売上実績に貢献できるよう活動している。
洗浄施工実績多数。
©2010 becantec Co.,Ltd.